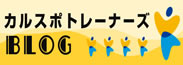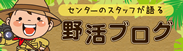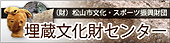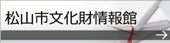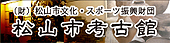投稿者の過去の記事1: hajiki
松山城三之丸跡18次調査③ |
松山城三之丸御殿の西側には、北御門広場と南北方向道路を区画する溝(東西溝)があり、前回の調査で東端が見つかりました。この溝は、三之丸御殿西側の側溝と道路の側溝の水が東西溝に流れ込む、三之丸内最大の溝(幅1.3m)であるこ … Continue reading
松山城三之丸跡18次調査② |
今回の調査地は、城山公園(堀之内地区)の西北部に位置します。過去に17回の確認調査が行われ、当時の松山城三之丸の様相が浮かび上がりつつあります。調査は古絵図を基にして調査場所を設定し、重機で近現在の造成土を掘削した後、人 … Continue reading
松山城三之丸跡18次調査① |
松山城三之丸跡18次調査は、史跡松山城跡保存整備に伴う埋蔵文化財の確認調査で、既往の確認調査成果と古絵図を参考に、北御門広場南側の東西方向に延びる溝と、その西側に位置する馬場付近の確認を目的に平成27年11月16日~同年 … Continue reading
小野地区の遺跡紹介24 『南梅本長広(みなみうめもとながひろ)遺跡1・2次調査』 |
縄文時代晩期~江戸時代の集落跡が見つかり、悪社川北岸の段丘上には長く人々が定住していたことがわかりました。鎌倉時代~江戸時代 の農業関連遺構と考えられる円形の土坑は、農業用の貯水施設として使用されたと考えられ、調査区内で … Continue reading
小野地区の遺跡紹介23 『南梅本上方(みなみうめもとかみがた)遺跡1次・2次調査』 |
鎌倉時代の掘立柱建物を構成する柱穴内には、土師器の坏や皿が納められており、建物の廃絶に伴う祭祀行為が行われていたことがわかりました。
小野地区の遺跡紹介22 『播磨塚(はりまづか)古墳』 |
古墳時代終末期の古墳で、巨石の面をそろえて造られた両袖式の横穴式石室であり、玄門を除いて巨石で構成されています。大刀 の柄頭や須恵器が副葬されていました。
小野地区の遺跡紹介21 『播磨塚天神山(はりまづかてんじんやま)古墳』 |
播磨塚の名は『播磨国風土記』・『古事記』・『日本書紀』に記載されている来目部(くめべの:久米部)小楯(おだて)の墓がこの地に造られたという伝承に由来しています。微高地上にはかつて20 数基の古墳が存在していたといわれ、古 … Continue reading
小野地区の遺跡紹介20 『水泥(みどろ)遺跡1~7次調査』 |
3次調査では、古墳時代後期の溝や柱穴が見つかり、調査地より南には集落が広がっていました。飛鳥時代~江戸時代の遺構には溝・土坑・柱穴・杭列・自然流路・水田址などがあり、時代を経て広い生産域をもつ農村集落が継続していました。 … Continue reading
小野地区の遺跡紹介19 『平井(ひらい)遺跡1~9次調査』 |
弥生時代前期~後期の土坑や溝などが見つかり、弥生時代を通して集落が営まれていたことがわかりました。
小野地区の遺跡紹介18 『下苅屋(しもかりや)遺跡1~4次調査』 |
自然流路 2次・3次調査では、古市遺跡から西流する自然流路の南岸や北岸が見つかりました。当地での流路幅は50m~80mにもおよぶもので、当時の河川交通にとって重要な川になっていて、川沿いにある弥生時代前期~ … Continue reading